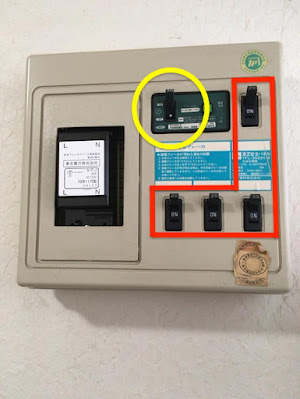スピーカーケーブル 太く短く確実に
スピーカーケーブルが音に影響するのは抵抗値だけです。
- 材質
- 太さ
- 長さ
- 末端処理
が考えられます。
抵抗値が周波数特性に影響する
- アンプにもスピーカーケーブルにも音色はありません。
しかし、アンプ(出力インピーダンス)+スピーカー(入力インピーダンス)+スピーカーケーブル(抵抗値)の組み合わせで周波数特性が変わります。スピーカーケーブルを変えて音が変わったら、
- ケーブルの抵抗値が変わった
ということになります。厳密にいうと「ケーブルの抵抗+末端処理(接触抵抗)」。価格や構造よりも、「抵抗値」だけに着目すればいいわけです。
※ アンプの「ダンピングファクター」について、こちらが分かりやすいと思います。
出典 技術資料:「ダンピングファクターは重要ではない」というオーディオの迷信 。
アンプ選びでは重要な要素となります。
ケーブルの抵抗を減らす方法
- 抵抗値の低い材質
- 抵抗値の低い太さ
- 抵抗値の低い長さ
- 抵抗値の低い末端処理
材質としては銀がもっとも抵抗値が低いですが、かなり高価です。やはり銅が現実的です。無酸素銅とタフピッチ銅では抵抗値が同程度なので、安いタフピッチ銅で充分。金は錆びないという利点がありますが抵抗値は銅に劣ります。
断面積が大きいと抵抗値が下がります。短く使うと抵抗値が下がります。撚り線のネジ締め接続よりも、半田、錫メッキの丸形・Y形圧着端子 などで確実に固定すると抵抗値は下がります。
- 接続端子と撚り線の接続は不安定
- スピーカー側とアンプ側の両方で不安定
1.撚り線をターミナルに直接接続すると、ネジの締め方・撚り方、剝き方、すべて音は変化します。同じケーブルでも作業結果で音が変わります。音質変化の原因がケーブルなのか、作業結果が不安定要素なので、その都度音が変わったように聞こえます。けっしてケーブルの音は変わっていません。
2.撚り線をターミナルにネジ止めするよりも、端子にハンダ付けしてからターミナルに接続したほうが良い結果をもたらすでしょう。異種金属での金属同士の相性もあります。特に金のターミナルと錫メッキでは錆びが出ることがあるのでコンタクトオイルなどで工夫が必要です。
以上のように、同じケーブルでも違う音になる要素は多々あるのです。「音質変化の根拠」を見極めないと良いケーブルやプラグを捨ててしまうかもしれません。
太く短く
断面積✕長さ。理論的にはそうなります。
しかし、太すぎると曲げにくいし、短すぎると掃除などで移動できないなど使いにくいものです。
- 1mなら1スケア
- 2mなら2スケア
- 3mなら3スケア
シンプルで分かりやすいですね。念の為アンプを選ぶときはダンピングファクターが40以上あればケーブルの影響は大差なくなるそうです。3m以下なら太さの影響は少ない筈。見た目や使いやすさ、好みで選びましょう。私は心配性なのでとりあえず5.5スケアを使っています。
キャプタイヤケーブルはHi-CP
安くて太いケーブル代表。スピーカーケーブルとして売られているわけではありませんが、CPは高いと思います。見た目が美しい高級品もいいですが、材質・太さ・許容電流など 仕様が提示されているものから選ぶのが無難でしょう。
3.5sqVCTの仕様(出典:オヤイデ電気)¥600/m 前後
構造 ・・・ 丸型キャプタイヤ
導体構成・・・3.5sq (45本 / 0.32mm) ×2芯
線材・・・タフピッチ銅
絶縁体(内部)・・・PVC
絶縁体(外部)・・・PVC
絶縁体標準厚・・・0.8mm
シース厚・・・1.8mm
仕上がり外径・・・12mm
許容電流・・・32A
耐電圧・・・600V(AC), 750V(DC)
連続導体許容温度・・・60℃
5.5sqVCTの仕様(出典:オヤイデ電気)¥700/m 前後
構造 ・・・丸型キャプタイヤ
導体構成・・・ 5.5sq (70本 / 0.32mm) ×2芯
線材 ・・・タフピッチ銅
絶縁体・・・(内部) PVC
絶縁体・・・(外部) PVC
絶縁体標準厚・・・ 0.8mm
シース厚 ・・・ 1.8mm
仕上がり外径・・・ 12mm
許容電流 ・・・ 32A
耐電圧・・・ 600V(AC), 750V(DC)
連続導体許容温度・・・ 60℃
- 「太いケーブルでは低音は増えるが高音が減る」?
という説。物理的には無理がある説。低音は減ることはあっても増えるとは考えにくいです。交換前と高感後の、相対的な聴感上の変化ではないでしょうか。細いケーブルでダンピングファクターの小さいアンプでは低音・高音が盛り上がって聞こえます。特性が変わってしまっています。そこで、太いケーブルに交換すると低音が減って聞こえるかもしれません。これは抵抗が減って正常な特性に近づいたことによるものです。高音も情報量が増えますが音量は減って聞こえるはずです。チープで細い音から伸びやかで豊かになる筈です。
スペクトラムアナライザーなどの周波数特性にはノイズや反射音・定在波の区別がありません。あくまでもリスニングルームでの周波数ごとの「音量」を表示します。音質と音量はイコールではありませんし、印象は違って聞こえます。テレビの映像に例えると、画面の大きさは同じでも、
- 2k
- 4k
- 8k
と情報量は違いますよね。抵抗値の低いケーブルも、音圧レベルは同じでも、音の解像度・情報量異なります。これを大きな違いと言う人もいれば、画面が大きくなければ意味がないという人もいるかもしれません。
実際に、5.5sqのケーブルを扱う作業は、被覆を剥くのも、銅線の先を揃えるのも、なかなかの力仕事になります。それこそ小さい端子には線が入り切らないし、ケーブル自体の重さでターミナルが壊れる可能性さえあります。私は軽くするために、このグレーの厚い被覆をすべて剥いて使っています。軽くなったからといって聴感上では区別できない程度、人間の耳では分からない程度です。
これ以上太いケーブルもあるでしょうが、実用には、このあたりが限界でしょう。
※ ケーブルの被覆を取るのは振動対策にマイナスだという話は聞いたことがあります。実際に実験してみると人間の聴力の範囲を下回っているようです。私は全く違いを感じませんでした。
接触抵抗による歪を減らす
末端処理です。私が、最初に5.5sqケーブルを使ったとき、音がイマイチだと思ったのは末端処理に問題があったようです。太いケーブルの一部分だけで接触していたり、撚り線接続がゆるゆるだったり。太いケーブルほど末端処理の影響は大きいようです。
- ボリュームを上げていくと、うるさくなる
- ボリューを上げていくと声に癖が付く
というのは全て接触不良による歪が原因でした。(周辺機器が故障はない)
平型端子やギボシの加締め、ハンダ、撚り線のほつれ、バナナプラグの取り付け方など、
- アンプの出力端子→スピーカーのターミナル→スピーカーユニット
まで、ケーブルの接続接点は様々なところにあります。
ケーブルの末端処理・締め直しで抵抗を減らすこと。
- 接触面積を増やす
- 接点の柔らかさ
- 撚り線のほつれ
- しっかり加締める
ハンダ付け・錫メッキの端子・撚り線の末端処理。処理後、情報量は増えて高音域の歪や低音のぼやけがなくなり、静寂でクリヤーな音。効果大で驚きました。スピーカーケーブルを交換する前にトライする価値はあります。スピーカーの自作派はスピーカーユニットからスピーカーターミナルまでの内部配線処理も見直す価値はあります。
接点数を減らす
アンプからスピーカーまでの接点は極力少ないほうがいいです。接点が増えると接触抵抗が増えます。少ないに越したことはありません。私は切り替え実験用に使っていたスピーカーセレクターとそれに接続していたプラグなど全て排除しました。オーディオとはレベルの違う話ですが、我が家のアンテナケーブルも屋根からの引き込みまでの接点をなくしたら利得30dBアップし、ブースター不要になりました。参考まで。
確実に固定する
スピーカーケーブルの購入には、皆さんそれなりに気を使っているようです。しかし、末端の固定がなされていない方が多いようです。ケーブルそのものを交換する前に、末端の固定をみ見直しただけで音質向上があるかもしれません。
1.錫メッキ端子で固定
Y型端子が使いやすさと機能性で最優秀だと思います。抵抗値の低さと、食いつきの良さが表面積も稼げます。
- ニチフ 裸圧着端子 Y形(100個入)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
スピーカー側。しっかり吸い付くように固定されます。
5.5sqのスピーカーケーブルをスピーカー端子に接続するならしっかり固定しないと接触不良が起きやすい。このY型端子は手で軽く締めるだけで、既にびくともしない。抜群に食いつきが良い。以前5.5sqをつないだときは高音域に癖が残っていましたが、このY型端子を使ったら過去イチの透明で繊細さがUP。5.5sqのケーブルはそのままでは太すぎるので、先端の被覆を剥いたら、撚り線を半分に分け、一方をケーブルの根本に巻きつけ、一方をY型端子に接続します。ばらつき・はみ出し注意、ハンダで固定します。
購入は、配管材料プロ トキワ 楽天店 https://item.rakuten.co.jp/haikanshop/2y8_5166/。
写真のスピーカージャックは金メッキ。錫メッキの端子と圧着するにはコンタクトオイルなどを塗布して異種金属の接触による錆対策をしておきます。https://souzouno-yakata.com/shop/2014/11/28/9294/#特徴。※ ソルダーレスは音を悪くする~オーディオ用バナナプラグの選び方- 出典: 創造の館さんにある末端処理の順位。
良い↑丸形、Y形圧着端子棒形圧着端子バナナプラグ (ハンダ)裸電線(メッキ)裸電線裸電線(メッキ)+ソルダーレスプラグ裸電線+ソルダーレスプラグ↓悪い
同じバナナプラグでもネジ式加締めとハンダづけではかなり分解能がかなり違います。ハンダ固定がより安定。
棒端子。導線用穴直径4mmと大きめ。長すぎ!グラグラ不安定!
このようなプッシュ式端子にはニチフフェルール。
長さ太さ色々あって勿論JIS規格品です。
フェルール用圧着ペンチが必要ですが。
ターミナル端子の軸に横穴が開いているものに棒端子を刺して締め付け固定できます
このようなターミナルにはY型端子もバナナも接続できます
Y端子は断面積も稼げて、食いつきも良い
2.バナナプラグは便利で実用的
バナナプラグは扱いやすさでナンバーワン。抜き差しが至って簡単。
・ サトーパーツ TJ-560
一体型構造が推しです。ケーブルを小さい穴に差し込む構造。ケーブルの差し込み穴径が2mmでAmazon14awgは入りませんでした。ケーブルの先端処理が必要です。ハンダ付が下手な私には難易度が高いです。(-_-;)
気になるのはバナナのバネが弱いこと。ジャックの大きさにもよるのでしょうが、私の場合は軽く引っ張るだけでするっと抜けてしまいます。
材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
耐電圧(V/min)AC500
定格(V)30 定格電流(A)3
適合規格RoHS対応
・ ELECTRO PJP DIYバナナプラグ:半田結線タイプ
こちらは穴径が2.3mmあり、更にハンダ付け用の横穴がありハンダ付けが容易になります。私はこちらがおすすめです。(しかし5.5sqのケーブルはギリ入りませんでした。(T_T))
(トキワエレネット・カタログ https://www.tokiwaelenet.jp/html/upload/pdf/product/0000030350046p_TA_vol5.pdf)
DIYバナナプラグ:半田結線タイプ
絶縁体:ポリアセタール
本体:真鍮ニッケルメッキ
スプリング:ベリリウム銅ニッケルメッキ
定格:500V AC、最大36A、<33V AC , <70V DC (IEC61010-031の定める測定基準による)
使用温度:-20℃~80℃
使用ワイヤー:導体-φ2.3mm、外径-φ5mm
音は、現在のところバナナプラグが一番使いやすいです。確実で動かない安定した接続は、同様に音もしっかりクリアーです。
アンプ(PMA−60)の背面端子。スッキリ・きっちり入っています。
DENON PMA-60にはY型端子が使えません。「ELECTRO PJP DIYバナナプラグ:半田結線タイプ」に落ち着きました。
接触抵抗(腐食)
コンタクトオイルを使う
異種金属の接触ではイオン化傾向の差による腐食が進みやすいようです。特に「金と錫」。金メッキターミナルに錫のY型端子など。私のバナナプラグはニッケルメッキですが念の為コンタクトオイルを塗布しておきます。音に何らかの劣化を感じたら、接点の腐食をチェックしてみるのも大事です。
筆や綿棒につけて塗っています。
半永久的に蒸発しないものもあるようです。
創造の館さんオリジナル電気接点を長持ちさせる~コンタクトオイル- 出典: 創造の館です。
撚り線・単線・芯線本数の違いは微小
ケーブルの断面積が同じであれば、撚り線だろうが、単線だろうが、本数が多かろうが、隙間があろうがなかろうが、抵抗値は同じになるはず。その他の効果も2〜3mのケーブルでは聽感上の違いはないようです(静電容量など)。にも関わらず音が変わるとすれば末端処理の問題か、ケーブルの記載データと実際の面積に多少の差異があるのか。ケーブルを始めオーディオ製品を購入するときは仕様データが公開されているものがおすすめです。(問い合わせに答えてくれるメーカーもあります)
聴感上 影響ない・無視できる要素
表皮効果、平行、ツイスト、スターカッド、…色々あります。物理的論理的に根拠はあるのですが、家庭で使う一般的なケーブルの長さ太さでは、人間が聞いて違いが分かるほどの違いはないレベルの話。些細なことに神経質になると時間と労力とお金の無駄になります。
ケーブルよりも音質変化が大きいセッティング
やはりスピーカーのセッティングです。セッティングで特性がかなり変わります。ケーブルとその末端処理で改善したならもう一度セッティングを見直して見ましょう。さらなる向上が期待できます。
ツイーターの間隔 1.2m、後は壁ギリ。
低音の量感があり周波数特性がよく聴きやすい。
↓
ツイーターの間隔 2m、後は壁から30cm。
解像度が上がり、落ち着き安定感を感じます。
これだけ違うと全く別のスピーカーのように聞こえます。思い切って大胆なセッティングをしてから、細かく詰めて行くのが良いと思います。
※ スピーカーの間隔を広げて壁側に20cm移動して部屋の幅x0.5に置きます。以下はピンクノイズによる周波数特性です。
更に奥に10cm移動して後の壁に押し付ける。こんなに特性が変わります。
次に、ほんの少し内側に向けるとこうなります
更に間隔を開いて、部屋の幅の7割に広げると低音も増えてステレオ感も増し大編成のオーケストラもスケール感がアップしました。
オーディオで最も音が変化するのは
1.スピーカーのセッティング
置き場所、高さ、スピーカーの間隔…。部屋の大きさや形に合った配置。同じスピーカーとは思えないほど変わります。まず
- 1メートル単位で大胆に変更。前後左右極端に替えてみます。
- 次は10センチ単位で変更
- 最後に10mm以下で調整
スピーカーの設置間隔
オルソン式では、部屋の幅の0.7。リスニングポイントはスピカーから0.9。いずれも絶対ではなく部屋の大きさによります。あくまでも目安です。スピーカーの背面は、ほぼ壁に押し付けからスタートです。
更にコーナーに吸音材などを置くと、定在波を押さえリスニングルームの癖を減らせます。材質にもよりますので、クッションや座布団などで実験してみてから購入を考えて見ましょう。
2.スピーカーの選び方
此処ではダイナミックにオーケストラやライブ会場のスケールをリスニングルームに再現したい向けのアドバイスです。つまりはスピーカーと2m以上離れて聴く場合です。
You Tubeで20cm以下小型スピーカーが低音の量感たっぷり、ダイナミックに鳴り響いているのを見かけます。しかしマイクのポジションがリスニングポイントでないものはそのまま鵜呑みに出来ません。至近距離では耳に入れるイヤホンでもある程度のスケール感は偉っるからです。
ヘッドホン・イヤホンは小口径・小音量なので耳につけないと使えません。スピーカーから2m以上離れて、同じスケール感を再現するなら大口径スピーカーが必要です。オーディオ製品で最も予算を割くべきところは「スピーカー」です。アンプは1万円のD級でもOKで、性能と値段は比例しません。予算で後悔しないためには38cm以上のウーファーとホーン型ツイーターの2Way、若しくはスコーカーを入れた3Wayは欲しいところです。100万円前後と高額ですが、買った人は一生に一度1セットしか買っていません。とかく自称オーディオマニアは入門機から初めて、アンプだスピーカーだ吸音パネルだと、買い替え買い足しに切りがありません。気がつくとトータルで100万を超える人が少なくありません。車のような消耗品ではないの最初から100万円のスピーカーを買っほうが後悔しないようです。但し、スピーカーとリスニングポイントが近いと大型スピーカーほど各ユニットの音がバラバラでまとまりません。将来大きな部屋似する計画がないなら、大型スピーカーは諦めましょう。視聴距離にあったスピーカーを買いましょう。
3.スピーカーケーブルやスピーカー端子の接続を見直す
物理的には些細な変化ですが、好みの音に近づく可能性があります。それでもだめならケーブルやプラグを考えましょう。
4.アンプやソース、プレーヤーの見直し
アンプには音色の無いものが理想ですが、ボリュームの安定性に問題があると、音量で周波数特性が変わったり、左右で音量が異なる(定位が狂う)場合もあります。その点、フルデジタルアンプではすべてフラットなものが期待できます。安いものは1万円程度から6万円前後とHiCP。ソースに至っては歪のない高音質ならデジタルです。Youtubeをはじめ動画サイトはデジタルソース。大編成のオーケストラも十分に良い音質が得られます。
5.参考サイト
感覚的、形容詞的表現は皆無。目からウロコの連続です。根拠となる計測データなどをわかりやすく、それを比較視聴で証明します。自称オーディオマニアこそ必見のサイトです。
・ ケンリックサウンド(https://www.youtube.com/c/KenrickSound)
空気録音がメインです。JBLのライブ感が素晴らしいです。こちらも実践型。比較視聴型。リスニングルームはは在庫スピーカーが左右壁側に沢山あり、およそ良い環境には見えません。ところが実際にiPhoneで空気録音したものでもハイクオリティー。1万円のアンプでもハイクオリティー。市販のJBLが更に超ハイクオリティーに生まれ変わっています。
クリアーで爽やか、膨よかな高音、ソフトで硬いピアノ、弾むベース、リアルなボーカル…。生き生きしています。JBL名機のレストアが本業のようですが、常に更なるハイクオリティーを追求しています。その方法は
- 徹底した歪の除去・抵抗値を下げる
銀単線ケーブルの向きや磁気のテストまで、ネットワークから電源、DAC…等など、使用機器は殆どオリジナル。無駄を省き、クリア+ピュアサウンドのためなら全てやろう…という徹底ぶり。お値段も桁違いですが ^^;。私は無謀にもこのケンリックサウンドに近づこうと日々研究中です^^;。
・出典:技術資料:「ダンピングファクターは重要ではない」というオーディオの迷信
ダンピングファクターってそいうことねとやっと理解できました。
追記 2022年9月18日
まだやり残したところがありました。おまけのジャンパープレートはペラペラで素材も正体不明で扱いづらい。スピーカーケーブルにYラグを圧着したものを自作。音質も多少向上するでしょうが、何より見た目が気になり交換。キッチリ固定でスッキリ。
異種金属なのでコンタクトオイルも塗りました。
不要になった、おまけのジャンパープレート
追記 2022年9月16日
「見た目と使いやすさ」でえらぶなら、CANAREのスピーカーケーブルも良さそうです。仕様表では抵抗値の低いものほど良いということになります。
CANAREのケーブル別の仕様表 からすると、
4s6--- 1mで 0.037Ω 3mだと 0.111Ω ------ ①
4s8--- 1mで 0.015Ω 3mだと 0.045Ω
電材堂さんによると、富士電線工業の VCT 5.5sq×2芯 600V の導体抵抗値は
VCT 5.5sq×2芯 600V 0.337 / 100m 、 3mだと 0.01011Ω ------ ②
①と②の差 が 0.1Ω。割合では約10分の一。音質にどれほど影響するのでしょうか。また、同じケーブルでの長さ1mの差は聴感に影響あるのでしょうか。値段と見た目のバランスでケーブルを選んで末端処理をキチンとしてターミナルにキッチリ固定すれば良いだけかもしれません。
CANARE 4s6黒は ¥240/m。VCT 5.5sq×2芯は ¥739 / m。
導体抵抗値ではVCT 5.5sqがCANAREを圧倒していますが、音も圧倒するかは個人の耳次第です。(^^)。
手間いらずで、そのまま使えるプラグ付き。2本セットなのでお手頃。
より線の先はハンダ付けですがプラグへの固定はハンダではなくネジ締めなのが残念。
※ 因みに実質導体断面積が気になる方はこちらのカナレのサイトを参考に
自分でプラグをハンダ付けしたい方には、切り売りもあります。
※ ざっとググってみた限りではVCTの 3.5sq、5.5sq よりも導体抵抗値の低いケーブルは見つかりませんでした。潜在メーカーさんは質の良いものがそれなりの価格で、オーディオショップさんでは見た目がよく売れる商品が好まれるでしょう。理論的には質優先ですが音質的には大差ないとも言えます。