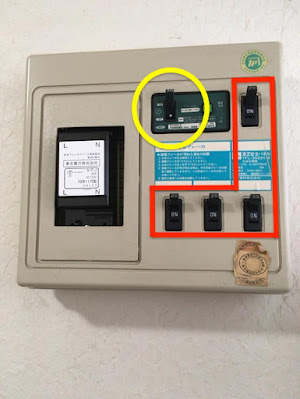ブラインドテストの経験ありますか?
人は思い込みで判断する
私はルームオーディオ愛好家です。一昔前まではスピーカーの音を録音しようなどという発想すらありませんでした。
最近のYoutubeにはユーザーの録音機器が向上したようで高音質のものが増えています。たまたまJBLスピーカーを扱った「ケンリックサウンド」のサイトを見つけました。
https://www.youtube.com/results?search_query=ケンリックサウンド。
「空気録音」(昔はマイクでの生録といった)で様々なJBLスピーカーを視聴できます。噂に聞くJBL特有のハイ上がりサウンドですが、サックスのキーを叩く音やリードの息遣い、硬くて透明なピアノ、バイオリンの胴鳴りや弦の擦れ金属音、ゴリゴリ・ゴシゴシのベース…。躍動感・空気感はじつに艶めかしくよく響く。余分なお金があれば4343辺りを一つ持っておきたい。このような音を出すにはどういう仕掛けがあるのか愛好家としてはとても興味をそそられます。単なるのドンシャリサウンドとは明らかに違うのです。抜けの良いハイ上がり。1kHzあたりにピークの山を作って、低音は量感控えめにしているのではとグライコで真似してみましたがそれだけでは無いようで本質的に何かが違う。簡単に真似できれば他社もぞくぞく生産するはずだし、ケチな私は自作に走る筈です。
そして「オーディオの化学」
更にJBLの音作りの根拠探し。スピーカーユニットの周波数特性やエンクロージャーは・・・などと情報をググっているうちに、「オーディオの化学」というサイトを見つけました。
http://www.ne.jp/asahi/shiga/home/MyRoom/Audio.htm。
感情的な形容詞で音の違いを論じてもしようがないと、化学や技術を根拠にオーディオを論じています。例えば、スピーカーケーブル交換による抵抗率の変化はその温度変化に因る抵抗率より低いため無駄だとか、超感上の音質変化を期待する以前の問題だと。いや、そうじゃないと言い張るなら、
- 「ブラインドテストをしたことがありますか?」
と言うのです。自分でケーブルだインシュレーターだと交換すると聞き方に思い込みが入るらしい。人間とはそういうものらしい。良くも悪くもそうらしい。気分や性格が大いに脳に影響するわけです。結果無限地獄にふりまわされて自分を見失い無駄にお金を注ぎ込む。
※「オーディオの化学」については科学的根拠に異論や間違いを指定する方々少なからずいらっしゃるようですが。人のアラ探し・間違い探しはもう沢山です。氏が仰る、正に「木を見て森を見ず」「鰯の頭も信心から」ということでは無いでしょうか。
確かに、言われてみれば大いに心当たりがあります。そして人に頼んでケーブルやらなにやらを交換しもらっても、ブラインドテストをしたことはないのです。処置してから人に聞いてもらうのです。(互いに音が変わったと思い込む)殆どのオーディオ愛好家がそうではないでしょうか。自分も全く自信がなくなりました。
確かに、何のアクセサリーを変えたからといって、アンプを変えたからといって、自分のスピーカーがJBLやTANNOYに変わったりしないことは容易に分かること。
そいういうことを考え始めたら私も冷静さを取り戻しました。Youtubeでの素晴らしいJBLケンリックサウンド再生しているのは、正に私のスピーカーD-70なのです。これが意味するところは、同じソースがあれば私のスピーカーでケンリックサウンドは再生できるということです。少し前の私なら本気でJBLを欲しいと考え始めるところですが、少し賢くなったので実は現状で十分だと気が付くわけです。ε-(´∀`*)ホッ
オーディオに於ける優先順位
オーディオに於いて最も重要なのはスピーカー。これがないと音が出ませんから。そしてその音質や個性はブラインドテストをするまでもなく誰でも違いがわかります。アクセサリーから音は出ません。ケーブルだのグッズにお金をかけるならそのお金をためて自分の理想に近づくスピーカーを手に入れるべきなのです。私もアンプやプレイヤーを幾つか買い替えて、いつの間にか高額の出費をしてしまいました。(T_T)
- 1万円のスピーカー+100万円のアンプ=1万円のスピーカーの音
- 100万円のJBL+1万円のアンプ=100万円のJBLの音
- スピーカーから耳に到達するまで
更にそのスピーカーシステムの性能に影響を及ぼすのはリスニングルームです。アンプやプレイヤーで補うには荷が重すぎます。リスニングルームの構造や大きさは簡単には変えられません。アンプやプレーヤーで音漏れや定在波は変えられまえん。数百万円かけるならリスニングルームを作って定在波のでない対策を出来るでしょう。誰にでも分かるほど効果があるでしょう。それが出来ないなら、スピーカーの配置や吸音材だけで妥協するしかないでしょう。
お金の無い私のようなリビングオーディオの妥協派はそれなりに楽しめばいいのです。小さいことに目くじら立てているとどんどん耳が、いや脳が悪くなります。吸音材、反射材、防振ゴムに…。オーディオ周りやがどんどん汚くなりやがて部屋が異様になります。見た目だけでもかなり音質は低下します。「オーディオの化学」の志賀@高槻さんも仰るように、『木を見て森を見ず』『鰯の頭も信心から』は戒めです。
※ 私のスピーカー位置を変更してみると、スピーカーの間隔を広げて壁側に20cm移動して部屋の幅の4分の1のポイントに置きます。。更に奥に10cm移動して後の壁に押し付ける。
こんなに特性が変わります。
※ スピーカー(セッティング)、部屋(反射吸音の偏り・定在波)、高音質のソース、そして変化が分かる耳(脳?)で音の変化は大きいと思います。
※ グラフィックイコライザーは単に周波数ごとの音量を変えるだけ。定在波・指向性・位相を改善できないので根本的な解決には向かない。
※ もともとスピーカーなどのオーディオ製品の特性はフラットに作られています。部屋の影響をもろに受けるのはスピーカーです。すぐ出来るのは、
- 位置(前後)
- 間隔(壁からの距離とスピーカー同士の間隔)
- 高さ(高音を耳の高さ)
※ ケンリックサウンドさんはオーバーホール・モディファイ・レストアが専門のようで製造中止の名品も販売しているようです。JBLといえば、ダンピングの効いた弾ける音、ピアノの硬いアタックなど、ライブ感。加えて、ケンリックサウンドでは、クオリティーのアップに尽力しているようです。クリアーでクオリティーの高い音作りをしています。JBLのグレードアップですね。日本人らしい取り組みです。Youtubeで純正JBLと思われる空気録音を幾つか聞きましたが、ケンリックサウンドのクオリティーの高い音(録音?)には及ばないような気がします。
※ 生のJBLは聞いたことがありません。Youtubeの空気録音だけです。
HPやYoutubeでケンリックサウンドを色々聞いていくうちにわかったことは
- 徹底して伝達効率を上げ、抵抗を減らして忠実再生にこだわっている
- 色付けや、小細工はしていない
- アンプは要素ではない